加茂野小学校いじめ防止基本方針
平成26年 4月1日策定
平成31年4月1日一部改訂
令和5年4月1日一部改訂
令和6年4月1日一部改訂
1 いじめの問題に対する基本的な考え方
(1)定義(法:第2条)
「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学に在籍している等当該児童生徒と一定の人間関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」とする。
(2)基本認識
教育活動全体を通じて、以下の認識に基づき、いじめの防止等に当たる。
・「いじめは、人間として絶対に許されない」
・「いじめをしない!させない!許さない!」
・「いじめは、どの児童生徒にも、どの学校でも、起こりうるものである」
(3)学校としての構え
・学校教育目標「豊かな心とやりぬく力をもつ加茂野の子」をうけ、「表情や仕草から相手の心を推し量り、誰もが仲間へのあたたかい言葉かけとあたたかい受け止めのできる心がもてる」児童の育成を目指す。
・全ての教職員が共通理解を図り、組織的な指導体制により対応することで、児童の心身の安全・安心を最優先に、危機感をもって指導に当たり未然に防止をしようとする意識を高め、早期発見・早期対応並びにいじめ問題への対処を積極的に行い、児童の心身の安定を図ることを目指す。
・日頃の教育活動を通し、児童に「いじめは人間として絶対に許されない」という意識を持たせると共に「いじめをしない、させない、許さない学校・学級づくり」を進め、児童一人ひとりを大切にする教職員の意識や日常的な態度を醸成することを目指す。
2 いじめの未然防止のための取組(自己肯定感を高める取組)
(1)「だれもが安心・安全・平等な生活」を送ることができる学校づくりを推進する。
(2)児童会重点活動の「だれにでもあいさつ」「安心・安全な生活」を推進することを通して、魅力ある学級・学校づくりの取組を推進する。
(3)「学校いじめ防止基本方針」の内容を周知徹底するために、各年度の開始時に児童生徒・保護者・関係機関等に公開する。
(4)QUの活用を推進する。
(5)インターネットを通じて行われるいじめに対する対策を推進する。
3 いじめの早期発見・早期対応のための取組
(1)アンケート調査等の実施を含めた的確な情報収集と校内連携体制の充実を図る。
(2)日頃から全ての児童理解に努めると共に、教育相談態勢の充実を図る。
(3)教職員の意識の高揚と計画的な研修により専門性を高める。
(4)保護者との連携を密にし、理解と協力を得ながら進める。
(5)いじめを中心とする生徒指導上の諸問題を学校だけで抱え込まず、日頃から教育委員会や加茂警察署、中濃子ども相談センター、民生児童委員、学校運営協議会委員等との連携を大切にする。
4 いじめ未然防止・対策委員会の設置
以下の委員により構成される「いじめ未然防止・対策委員会」を設置する。
学 校 職 員:校長、教頭、生徒指導主事、学年主任、教育相談主任、養護教諭等
学校職員以外:必要に応じてメンバーを編成する。
5 いじめ問題発生時の対処
(1) いじめ問題発生時・発見時の初期対応
【組織対応】
・「いじめ未然防止・対策委員会」で方針を確認し、事実確認や情報収集、保護者との連携等、役割を明確にした組織的な動きを作る。
【対応の重点】
・いじめの兆候を把握したら、即刻情報を共有し、組織的にかつ丁寧に事実確認を行う。いじめの事実が確認できた、あるいは疑いがある場合には、いじめを受けた(疑いがある)児童の気持ちにより添い、安全を確保しつつ 情報を収集し、迅速に対応する。
・いじめに関する事実が認められた場合、教育委員会に報告するとともに、いじめた側といじめを受けた側の双方の保護者に説明し、家庭と連携しながら児童への指導に当たる。
・保護者との連携のもと、謝罪の指導を行う中で、いじめた児童が「いじめは許されない」ということを自覚するとともに、いじめを受けた児童やその保護者の思いを受け止め、自らの行為を反省する指導に努める。
・いじめを受けた児童に対しては、保護者と連携しつつ児童を見守り、心のケアまで十分配慮し、二次被害や再発防止に向けた中・長期的な取り組みを行う。
(2) 重大事態と判断された時の対応
・いじめにより児童の生命、心身又は財産に重大な被害が生じた疑いがあると認めるとき、いじめにより児童が相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるとき等については、教育委員会の指導の下、加茂警察署をはじめとする関係機関と連携を取って指導に当たる。
(3)いじめの解消の定義
・いじめは単に謝罪をもって安易に解消するとはいえず、解消している状態とは、「いじめ行為がやんでいる状態が3か月継続」「被害者が心身の苦痛を受けていない」という2つの条件を満たしているものとする。
6 学校評価における留意事項
・いじめを隠蔽せず、いじめの実態把握及びいじめに対する措置を適切に行うため、学校評価において次の2点を加味し、適正に学校の取組を評価する。
①いじめの早期発見の取り組みに関すること
②いじめの再発を防止するための取り組みに関すること
7 個人情報等の取り扱い【個人調査(アンケート等)について】
・いじめ問題が重大事態に発展した場合は、重大事態の調査組織においても、アンケート調査等が資料として重要となることから、5年間保存する。
8 いじめ防止等に関する年間計画
| 学期・月 | 行事・研修等 | いじめ
対策委員会 |
未然防止の
取り組み |
早期発見の
取り組み |
人権教育等の取り組み | 諸機関との
連携 |
|
| 前 期 | 四月 | 入学式
1年生を迎える会 |
いじめ防止基本方針の策定
定例「いじめ対策委員会」 |
校内研修
「いじめ防止基本法」 学級づくり |
だれにでも明るくあいさつすることができる。 | 授業参観および保護者懇談会 | |
| 五月 | 保護者との個人懇談 | 定例「いじめ対策委員会」 | 学級づくり
|
教育アンケート
ハイパーQ-U実施 |
|||
| 六月 | 定例「いじめ対策委員会」 | 校内研修
リレーションづくりをめざした授業① |
教育アンケート
第1回教育相談 |
集団でのきまりを守って生活することができる。 | 幼保小連絡会
授業参観および保護者懇談会 |
||
| 七月 | 定例「いじめ対策委員会」 | ||||||
| 八月 | 定例「いじめ対策委員会」 | 校内研修
リレーションづくりをめざした授業② |
|||||
| 九月 | 定例「いじめ対策委員会」
前期のまとめ |
教育アンケート
|
|||||
| 後 期 | 十月 | 前期終業式
後期始業式 運動会 |
後期の方針
定例「いじめ対策委員会」 |
ハイパーQ-Uの実施
教育アンケート |
|||
| 十一月 | 人権週間
|
定例「いじめ対策委員会」 | 校内研修
リレーションづくりをめざした授業③ |
第2回教育相談 | 人権集会に向けての取り組み | 幼保小連絡会
|
|
| 十二月 | 人権集会
|
定例「いじめ対策委員会」 | 人権集会 | ||||
| 一月 | 定例「いじめ対策委員会」 | 個の成長と課題を明確にする。
教育アンケート |
いつでもどこでも誰にでも挨拶できる。 | 幼保小連絡会 | |||
| 二月 | 感謝の会
6年生を送る会 |
定例「いじめ対策委員会」
今年度のまとめ 来年度の方針 |
自分のまわりの人に感謝の気持ちを持って生活できる。 | 幼保小連絡会
授業参観および保護者との懇談会 |
|||
| 三月 | 卒業式
修了式 |
定例「いじめ対策委員会」 | 校内研修
研修のまとめ |
幼保小連絡会 | |||
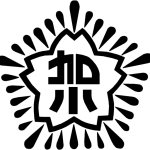 美濃加茂市立加茂野小学校
美濃加茂市立加茂野小学校 











